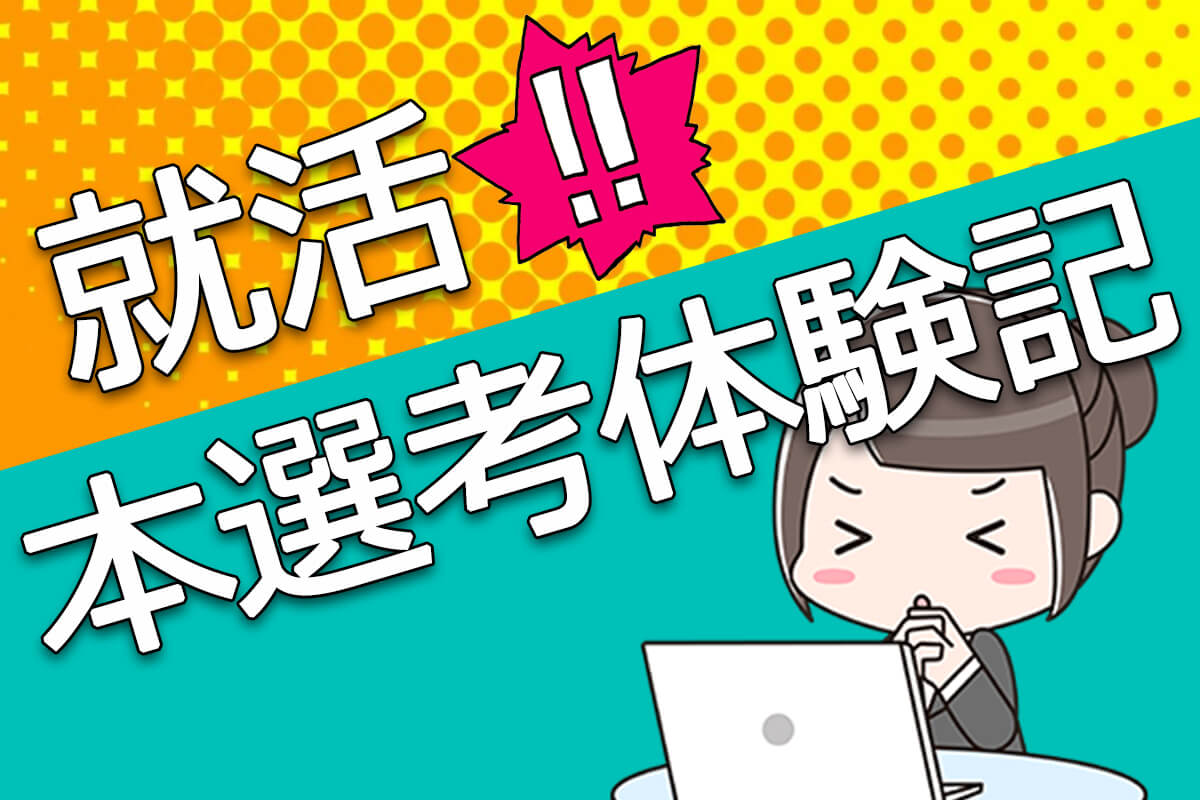川澄化学工業株式会社の就活本選考体験記(2021年卒,研究開発職)です。先輩の体験記を参考にして、就活を有利に進めましょう!
就活本選考体験記一覧
| 会社名 | 川澄化学工業株式会社 |
|---|
| 部門(職種) | 研究開発職 |
|---|
| 卒業予定年/卒業年 | 2021年 |
|---|
| 内定(内々定)が出た時期 | 修士2年の4月 |
|---|
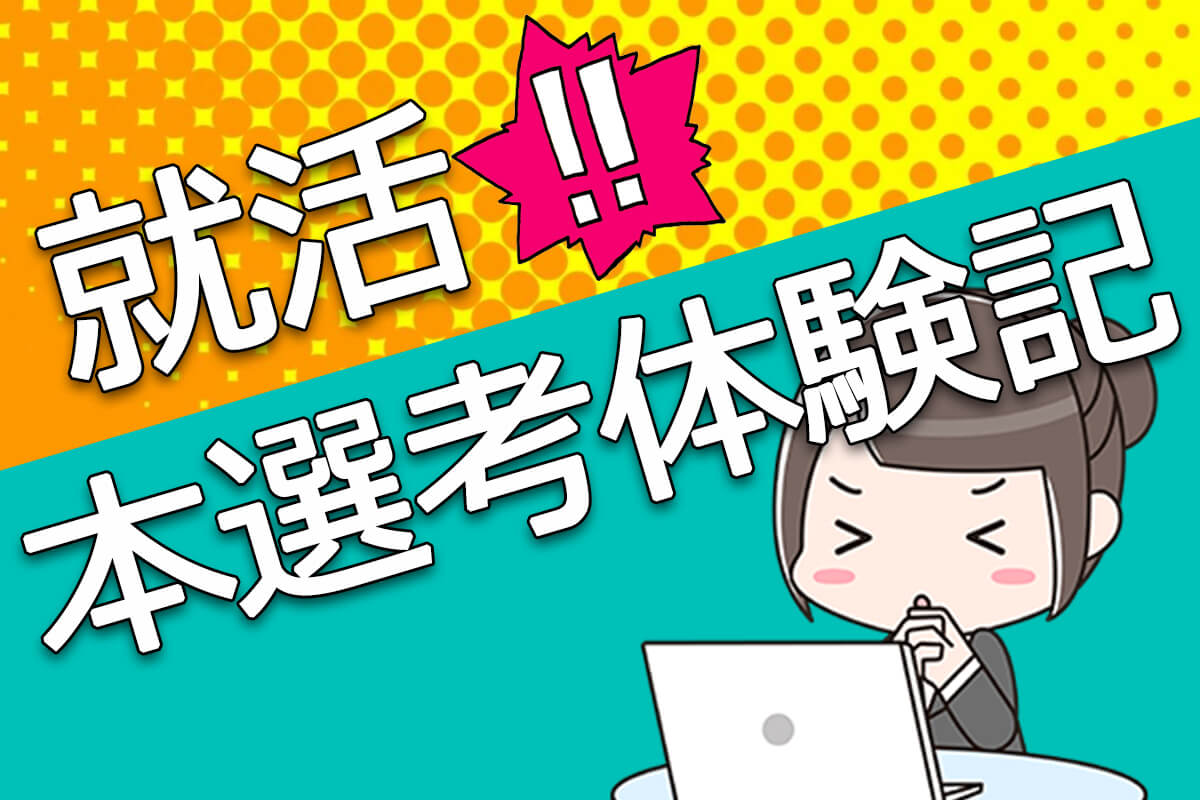
選考フロー
ES・Webテスト→一次面接→二次面接→最終面接
説明会
参加時期
3月
形式、選考への影響、感想など
選考を受けるにあたって必須、Web上での視聴形式だったので参加できないなどはなかった
エントリーシート
提出時期
修士1年の3月
提出方法
Open ES + 企業独自の質問
設問、文字数
研究内容(150)、自己PR(400)、学生時代に最も力を入れて取り組んだこと(400)、志望動機(400)
結果連絡の方法、日数
リクナビを介して、1週間程度
留意したポイント、アドバイスなど
自身のアピールポイントとエピソードにおける成果・結果が一致していて論理的な文章が書けているかに注意した。
筆記試験
受験方法
webテスト
内容や難易度
計算問題と文章問題が多め。文章題に対する耐性をつけとくと良いと思う。
結果連絡の方法、日数
リクナビを介して。一週間程度
一次面接
同時に面接を受けた学生の人数
1人
面接官の人数、役職など
2人(人事・人事部長)
時間
30分
質問内容や進め方
最初に自己prについて3分間で発表し、
それに対して深掘りがある。3分の発表については作製した資料を持ち込んでも良い。(私の場合は用いなかったが)
雰囲気
穏やか
留意したポイント、アドバイスなど
エピソードとPRポイントの一貫性を大切にした。自分の強みが何で、なぜそれを強みとして言えるかのように強みを論理的にアピールできるようにした。
結果連絡の方法、日数
リクナビを介して、1週間程度
二次面接
同時に面接を受けた学生の人数
1人
面接官の人数、役職など
2人(技術系の部長・人事部長)
時間
30分
質問内容や進め方
最初に3分間で自分の研究(+研究で何を頑張ったか)について発表があった。その後はそれに対する深掘りがメイン。また人事部長は一次面接と同じ人だったので、一次面接の時に発表した内容についてももう一度聞かれ、深掘りされた。
雰囲気
穏やか
留意したポイント、アドバイスなど
研究内容だけでなく、研究の中のどこに自分らしさがあったか、何をどう頑張ったかを意識した。一次面接と同じく論理性を大切にした。(理系であればあって当然という風に認識されるだろうと予想していたため)
結果連絡の方法、日数
当日。電話にて
三次面接(最終面接)
同時に面接を受けた学生の人数
1人
面接官の人数、役職など
2人(人事部長・役員の方)
時間
30分
質問内容や進め方
最初に3分間で自己PRについて発表を行い、それに対する深掘りがメインだった。勤務地について研究所が川崎にできるが、九州の現研究所にもいくことも多いかもしれないが大丈かと聞かれた。
雰囲気
穏やか
留意したポイント、アドバイスなど
最終面接だが、気後れせずにやり切ろうという思いで望んだ。最終面接でもWeb開催だったため、少し大袈裟に反応(相槌など)を意識した。
結果連絡の方法、日数
当日。電話にて
内定後
同じ部門の内定者数は何人くらいか
詳しくは不明だが10人程度だと予想される
内定後の拘束状況
5月上旬までに内定承諾書を提出(悩んでいるようならその旨を伝えれば提出を遅らせることは可能とのこと)
OB訪問
内定先企業にOB訪問したか
しなかった
インターンシップ
内定先企業のインターンに参加したか
参加した
いつ頃、どのくらいの期間参加したか
修士1年の12月、1日間
大まかな内容
企業理解、業界理解について。社員の方との座談会もあった。
選考と関係あったか
あり(早期選考で他の人よりも早い日程で選考が始まったが、内定のもらえやすさに直接関わるかは不明)
この企業の選考全体を通して
企業研究をどのように行いましたか?
中期経営計画書に目を通して、会社が全体としてどのような方向に進んでいこうとしているのかについて理解しようとした。それと同時に社員の方と話すことで一人一人はどのようなことを行っているのかについて理解を深めた。会社の方向性と社員の方の仕事の現状の2つに重点を置いて行った。
選考で重視していたと思われる点は何ですか?
しっかりと自分の考えを論理的に話すことができるかどうか(3分の発表→深掘りがほとんどだったため、そのように感じました。)
この内定先の社員や内定者にはどんな人が多いと思いますか?
真面目な人が多いと感じました。
おすすめの選考対策、アドバイスがあれば教えてください。
どのような仕事をしているかだけでなく、会社がどのような方向へ進もうとしているかについて調べるのは大事だと思いました。(技術系・研究系であれば新たな分野に注力している企業がほとんどですので、そこがどのように違うか、どんな特徴があるかをはっきりさせておくといいと思いました。)
会員限定コンテンツです。
これより先をお読みになる場合には会員登録/ログインが必要です。